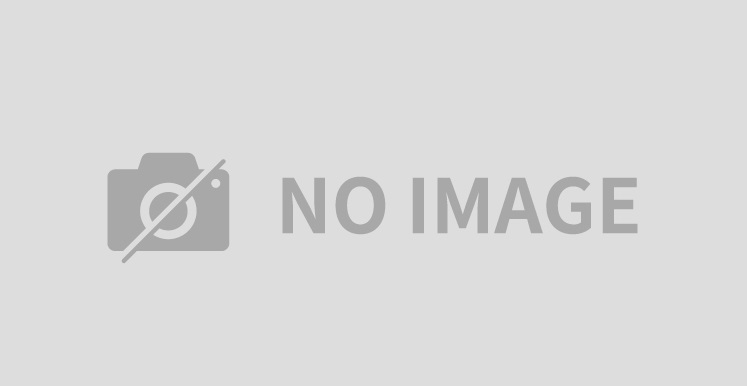前回は古典に見る大地震の記憶-1として、1185年(元暦二年)に京都周辺で発生した大地震「文治地震」に関する『方丈記』と『平家物語』の記述を紹介した(震源地は琵琶湖西岸あるいは南海トラフなど諸説あり不明。直後に「元暦」から「文治」に改元されたため「文治地震」と呼ばれる)
今回は南北朝時代の1361年に西国で発生した大地震。北朝の元号「康安」ではなく、南朝の元号「正平」をもとに「正平地震」と呼ばれる大地震で、南海トラフ沿いが震源とされ、東海道沖の地震も連動したと推測されている大地震である。連続的に地震が発生しており、現在の徳島県海部郡美波町や大阪の難波沖、さらに山口県の周防あたりで見られた現象や、京都周辺や熊野参詣道の様子などの記述が『太平記』に出てくる。
以下にこの大地震について『太平記』に記述された原文を引用する(出典:『太平記』作者不詳。兵藤裕己校注。岩波文庫。全六巻)。岩波文庫の第五巻、『太平記』では第三十六巻の『大地震并(ならび)に所々(しょしょ)の怪異(けい)、四天王寺金堂顚倒(してんのうじこんどうてんとう)の事』の記述である。( )内に岩波文庫における原文の振り仮名と脚注、および私の補注を記した
『同じき元年(康安元年。西暦1361年のこと)六月十八日の巳刻(みのこく、午前十時頃)より、同じき十月に至るまで、大地おびただしく動いて、日々夜々(ひびよよ)止(や)む時(とき)なし。山崩れて谷を埋(うず)み、海傾(かたぶ)いて陸地(くがち)となりしかば、神社仏閣(ぶっかく)倒れ破れ、牛馬人民(ぎゅううばじんみん)の死傷する事、幾千万(いくせんまん)と云う数を知らず。山川(さんせん)、江河(こうが)、林野(りんや)、村路(そんろ)、この災(わざわ)ひに逢はずと云ふ処(ところ)なし
中にも、阿波(あわ)の雪(ゆき。現在の徳島県海部郡美波町東由岐)の港と云ふ浦には、俄(にわ)かに太山(たいざん)の如くなる潮漲(しおみなぎり)り来たって(山のごとき津波が押し寄せたということ)、在家一千七百余宇、悉(ことごと)く引く塩(しお。津波の引き潮のこと)に連れて海底に沈みしかば、家々にあらゆる処の僧俗(そうぞく)、男女(なんにょ)、牛馬、鶏犬(けいけん)、一つも残らず底の藻屑(もくず)となりにけり
これをこそ希代(きたい)の不思議と見る処に、同じき六月二十二日に、俄(にわ)かに天掻(か)き曇り、雪降りて、吹寒(すいかん)の甚(はなは)だしき事、冬至(とうじ)の前後の如く、酒を飲みて身を暖め、火を焼(た)いて炉を囲む人は、自(おの)づから寒(かん)を防ぐ便り(たより。手だて、方法のこと)もある。山路(さんろ)の樵夫(しょうふ。きこりのこと)、野径(やけい。野道のこと)の旅人、牧馬林鹿(ぼくばりんろく。牧場の馬や林の鹿のこと)は悉(ことごと)く氷に閉ぢられ、雪に臥(ふ)して死する者数(かず)を知らず
七月二十四日には、摂津国難波(せっつのくになにわ)の浦の沖数百町(一町は約109メートル)、半時ばかり(1時間ほど)乾き上がりて、無量の魚(うお)ども沙(いさご。砂底のこと)の上に吻(いきつ)きける程に、あたりの浦の海人(あま)ども、網を巻き、釣(つり)を棄て、われ劣らじと拾いける処(ところ)に、また俄(にわ)かに大雪山(たいせつざん。天竺の高い山々。ヒマラヤのこと)の如くなる潮(しお。波)来たって、漫々たる海になりければ、数百人の海人ども、生きて帰るはなかりけり
また、周防(すおう。現在の山口県)の鳴門(なると)、俄(にわか)かに潮去って陸(くが)となる。高く峙(そばだ)つたる岩の上に、筒(つつ)のまはり二十丈(じょう。一丈は約3メートル)ばかりなる大鼓(たいこ)の、銀(しろがね)の鋲(びょう)をしげく打って、面(おもて)には巴(ともえ)を書き、台には八龍を拏(ひこずら)はせたる(台に仏法守護の八大龍王をからめて描いたのが)、顕(あらわ)れ出でたり。暫(しばらく)くは、見る人これを懼(おそ)れて近づかず。三、四日を経て後、近きあたりの浦人(うらびと)ども、数百人集まって見るに、筒は石にて、面(おもて)をばいかなる物にて張りたりとも見えず、鉄(くろがね)を延べたるが如し。尋常(よのつね)の撥(ばち)にて打たば、よも鳴らじとて、大きなる撞木(しゅもく。大鐘をつく棒のこと。正しくは「橦木」。読みは同じ「しゅもく」)を拵(こしら)へて、大鐘を突くようにつきたりけるに、この大鼓、天に響き、地を動かして、三時ばかりぞ(約6時間)鳴りたりける。山崩れて谷に答え、潮湧いて天に漲(みなぎ)ってければ、数百人の浦人ども、ただ今大地の底へ引き入れらるる心地して、肝魂(きもたましい)も身に添わず、倒るるともなく走るともなく、四角八方(しかくはっぽう)へぞ逃げ散りける。この響き、余所(よそ)へなほ動いて、京中まで聞こえ、左右なく(そうなく。すぐにはの意味)止まらざりければ、世には、「天の鳴動(めいどう)するか、地の震裂(しんれつ)するか、雷(いかづち)のなるか、将軍塚か(しょうぐんがづか。京都市東山区華頂山頂の塚のことで、桓武天皇が平安京鎮護のために八尺の将軍像を埋めたと伝え、天下に異変のある時しばしば鳴動したとか)」など、色々にぞ申しける。その後よりは、いよいよ近づく人なかりければ、天にや登りけん、また海中へや湧き入りけん、潮は本(もと)の如くに満ちて、大鼓は見えずなりにけり。(中略)
洛中、辺土(へんど)には、傾(かたぶ)かぬ塔の九輪(くりん。塔の最頂部に立てる九重の金具の輪)もなく、熊野参詣(くまのさんけい)の道(天王寺から熊野三山へ向かう参詣路。紀伊路から中辺路のこと)には、地の裂けぬ所もなかりけり。旧記(きゅうき。古い記録)に載(の)する所、開闢以来(かいびゃくこのかた)未だかかる不思議なければ、この上に、またいかなる世の乱れか出(い)で来たらんずらんと、怖(お)ぢ恐れぬ人は更になし』
お読みになった方は、どのように思われただろうか。これらの大地震の多く、特に海岸沿いで起きた波の挙動などは、東日本大地震の津波に勝るとも劣らぬ激しい動きを見せているように思われる
『太平記』には古今和歌集、源氏物語、平家物語などの日本の書や、史記や諸子百家、項羽と劉邦の楚漢戦争、唐の安禄山の乱、白居易(白楽天)の漢詩などの中国の書や故事が頻繁に引用されており、作者の博識さに感心させられるばかりだ(一方で知識の「ひけらかし」のようにも感じられてしまうのも否めない)。後述するように、『太平記』の原型の著者である恵鎮が僧侶であることから、仏教経典の用語や引用、神がかり的(超常現象的)あるいは宗教的な色彩が濃い描写が多いのも特徴だ
例えば、周防(すおう)の鳴門(なると)で海底から現れた「大鼓」に関する記述などは、誇張された表現に加え、不可思議な出来事として脚色もされており、実際にどのような自然現象が起きたのか分かりづらい
大きな引き潮で海底から巨大な岩が現れるのは想像できるが、それを大きな太鼓に見立てて、わざわざ橦木(しゅもく)を作って鐘を突くようなことをするとは思えない。突いた後に、三時(さんとき、6時間)も鳴り続け、音が次第に移動していったというのも理解しがたい
ひょっとすると、阪神淡路や東日本大地震で目撃したよりもさらに想像を超える現象が起きたのだろうか。たとえば、沈み込む地下のプレートに押された大地が一気にではなくゆっくりと戻った際の音が響き続けたとか、あるいは断層による亀裂が連続して発生し徐々に伸びていったとか・・・
波の挙動については、渦潮の現象を起こす瀬戸内の複雑な地形や、内海と外海の海流のぶつかり合いなどによって、東日本大地震とは違った引き潮や津波の現象を引き起こしていたのかもしれない
日本には各地に地震に関するいろんな伝承が伝わている。口伝の場合は時間とともに変容していくことが多いが、各地の古文書に残る記録は当時の状況を比較的正確に伝える。今回紹介した古典にあるのと同じような震災の記述が多くみられることは良く知られている。古人がせっかく残してくれた過去の記録をしっかりとひも解き、現代に生きる我々は用心するに越したことはない
<蛇足>
最後に『太平記』に描かれた時代について触れておきたい。『太平記』は、北条氏による執権政治の末期に、当時の後醍醐天皇が武家から政治を取り戻そうと企て、打倒北条を諸国の武士に働きかけるところから始まる(1324年)。企てが露見し、北条幕府により後醍醐天皇は隠岐の島へ遠島となり、幕府は光厳天皇を立てる
天皇家においては、ともに後嵯峨天皇を始祖とする大覚寺統と持明院統の間で以前より皇位継承の対立があり、幕府が仲裁に入り「文保の和談」として皇位継承ルールが取り決められた。10年の皇位在位期間を経て同じ統派の皇太子に譲位し、その10年後にはもう一方の統派の親王に天皇位を譲り、さらに10年後にその統派の皇太子に譲位する。そしてまた、10年後にもう一方の統派に皇位を戻し、皇位を交替で継承するという取り決めがなされていた
大覚寺統の後醍醐天皇の皇太子(邦良親王)が早世したので後醍醐天皇が続投したが、持明院統側は皇位を渡すべきだと主張していた。後醍醐天皇の倒幕計画の発覚に伴い、幕府は後醍醐天皇を退位させて隠岐へ移し、上記のルールに従って持明院統の量仁親王を光厳天皇としたのであった
一方、北条政権は政治を疎かにして豪奢に耽り、朝廷のみならず武家社会においても少なからぬ反感を買っていた。そんな中で後醍醐が隠岐から脱出し、天皇として再度実権を取り戻すべく動き出す。清和源氏の流れをくみ、鎌倉幕府の筆頭御家人である足利高氏(後に尊氏)が後醍醐天皇に内応して挙兵し、京都の南と北にある幕府の六波羅探題(朝廷などによる反幕府活動を監視して取り締まる機関)を滅ぼす。同じく清和源氏の流れをくむ新田義貞も挙兵し、関東のほとんどの幕府御家人が次々と倒幕に動き、北条政権は滅ぼされる(1333年)
しかしながら、この過程において、天皇による治世へと戻ることにより武家がパワーを失うことを嫌い、足利尊氏をリーダーとする勢力は野心旺盛な大覚寺統の後醍醐天皇を捨て、武力を背景に持明院統の光厳天皇を支持し、幕府による政治を維持しようとする
天皇家は、吉野に逃れた後醍醐天皇の南朝と、足利によって庇護された北朝(京都を拠点)に分かれて正統を争い、数代にわたってしばらく二人の天皇が存在する世が続く。後醍醐天皇の南朝方には楠木正成などの忠臣や新田義貞をリーダーとする勢力が味方し、天皇家、武家、さらには対立する宗派の寺院の間で争いが繰り広げられた
とりわけ武力をもつ足利と新田の争いは世代を超えて壮絶な戦いとなる。もともと北関東で隣りどうしの新田(上野国。現在の群馬)と足利(下野国。現在の栃木)は、源氏の跡目や武家の覇権をかけ、争いは熾烈を極めた。やがて覇権を争ううちに、同族の中でさえも兄弟、親子が南朝についたり北朝についたりと敵味方に分かれて争い、出口の見えない混沌とした争乱の世の中になっていく
南北朝時代は、京の都や近畿をはじめ、日本のあちらこちらで戦火が上がり、日本が未曽有の混乱に陥った時代である。源氏と平氏が争った平安時代と同じく、戦災だけでなく、飢饉や疫病、大地震などの天災にも襲われた
『太平記』の記録は、後醍醐天皇の北条幕府転覆の企てから始まり(1324年)、足利と新田の世代を超えた長い戦いの後に勝敗が決着していく過程を描き、室町幕府の二代目の足利義詮(尊氏の子)が亡くなって、幼少の足利義満(義詮の子)を三代目にするところで唐突な感じで終わる(1367年)
この時点では南朝の天皇は存続しており、九州は南朝方の勢力が支配し、世の争いは完全に終息していない。南朝から皇位の象徴である「三種の神器」が北朝に引き渡され、南北朝時代が終焉して北朝の世となったのは1392年である。実に室町幕府三代目の足利義満の治世が終わろうとする頃である
『太平記』の原作者や成立の過程については未だ謎が多い。法勝寺の恵鎮が大本の作者で、二十余巻といわれる原型となるものを書き上げ、それを足利尊氏の弟の足利直義のもとに持参したと言われている
この時、すでに足利兄弟は敵味方に分かれており、弟の直義は南朝方についていた。後に直義は兄の尊氏に殺される。一方、恵鎮の『太平記』原型は室町幕府の手に渡り、いつしか足利政権樹立の記録としての役割を帯びていく。足利にとって都合の悪い記述内容だったとされる第二十八巻は丸ごと削除されて欠巻となった
その後、幕府方の別人(複数?)によって編纂が続けられ、鎌倉幕府から室町幕府が誕生する全四十巻の歴史書としてまとめられたと推測されている(現在までに伝わる写本は、第二十八巻を欠巻として残し全四十巻とするか、あるいは巻を繰り上げて附番し全三十九巻としている)
長い動乱の歴史、しかもまだ完全に終息に至っていない歴史の記録をあえて『太平記』と題したのは、何ともシニカルなネーミングに思える