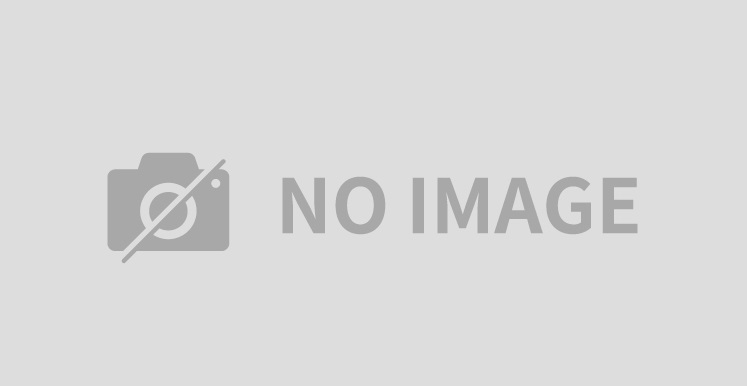3.11の東日本大地震発生から10年を迎えようとしている。メディアでは当時を振り返る特集や、現状のレポートなどが増えてきた
「天災は忘れた頃にやってくる」というのは、夏目漱石門下の物理学者、寺田寅彦の名言であるが、メディアだけでなく、自然からも忘れることが無いよう警鐘を発するかのように、福島沖でマグニチュード7.3の地震が発生した
私の住まいは東京ディズニーランドの近くで、今回の地震発生時はすでにベッドで眠りについていた。久しぶりに携帯のアラームが鳴り響き、揺れが始まったのは午後11時過ぎ。3.11のときのように長く揺れが続き、あの時を思い出して身構えた
世の中、コロナ一色ともいえる状況で、第三波がようやく減衰してきたものの、PCR検査の処理能力や保健所で対応する仕組み、病床のひっ迫など、第一波からほとんど改善されていない状況に、苛立ちを覚えておられる方も多いだろう
今一度、あの震災について振り返った時、10年が経過した今になっても、万一の対応準備が大きく進んでいるとはとても言いがたい状況だ。天災は繰り返しやってくるのだ。東北の堤防を嵩上げすることだけが対策ではあるまい。ソフト・ハード両面から日本各地の自治体が中心となって、可能な限りの対策を講ずるとともに、企業や個人も不測に備えた準備を急ぎたいものだ
以前、このブログで平安時代に書かれた鴨長明の『方丈記』に、京の都を立て続けに襲った天災の記録があることを紹介した(「Covid-19に思うこと-7」☜クリック)
1177年:安元の大火。御所を含め京都の3分の1が焼失
1180年:治承の竜巻。北から南へ都を縦断。多くの家、神社仏閣が倒壊
1181年:養和の飢饉。台風や日照りで不作が続く。
1182年:疫病の大発生。都の中心だけで4万人以上が死亡
1185年:元暦の地震。京都の北東部を震源として阪神淡路大震災級の地震が発生
因みに1181年は平清盛が亡くなった年で、1185年は平家が壇ノ浦の戦いに敗れて滅亡した年である
『方丈記』は、『平家物語』の時代、まさに源氏と平氏が争い、平氏が滅んでいく時代に、上記のごとく、京の都とその周辺で次々と発生した大火、竜巻、飢饉・疫病、大地震という天変地異を記録している
今回、改めてその記述をそのまま紹介したい。まずは以下に原文を引用する
(出典:『方丈記』鴨長明。浅見和彦校訂・訳。ちくま学芸文庫)
『また、同じころかとよ、おびただしく大地震(おほなゐ)振ること侍(はべ)りき。そのさま、世の常ならず。山はくづれて、河をうづみ、海はかたぶきて、陸地(ろくぢ)をひたせり。土裂けて、水湧(わ)きいで、いはほ割れて、谷にまろびいる。なぎさ漕(こ)ぐ船は波にただよひ、道ゆく馬は足のたちどをまどはす。都のほとりには、在々所々、堂舎塔廟(たふめう)、ひとつとしてまたからず。或(あるい)はくづれ、或(あるい)は倒れぬ。塵灰(ちりはひ)たちのぼりて、さかりなる煙の如し。地の動き、家のやぶるる音、雷(いかづち)にことならず。家の内に居(お)れば、たちまちにひしげなんとす。走りいづれば、地割れ裂く。羽なければ、空をも飛ぶべからず。龍ならばや、雲にも乗らむ。おそれの中におそるべかりけるは、ただ地震(なゐ)なりけりとこそ覚え侍りしか。(中略)
かく、おびただしく振る事は、しばしにてやみにしかども、そのなごり、しばしは絶えず。世の常、驚くほどの地震、二、三十度振らぬ日はなし。十日、二十日過ぎにしかば、やうやう間遠(まどほ)になりて、或いは四、五度、二、三度、もしは一日まぜ、二、三日に一度など、おほかたそのなごり、三月ばかりや侍りけむ。
(中略)むかし齊衡のころかとよ。おほなゐふりて、東大寺の佛のみぐし落ちなどして、いみじきことゞも侍りけれど、猶このたびにはしかずとぞ。すなはち人皆あぢきなきことを述べて、いさゝか心のにごりもうすらぐと見えしほどに、月日かさなり年越えしかば、後は言の葉にかけて、いひ出づる人だになし』
以下に訳文を引用する(出典は同上)
『また、同じころであったが、すさまじい大地震がありました。そのさまはいつもの地震とは全く違っていた。山は崩れ、河を埋め、海は傾いて、陸地を水びたしにしてしまった。大地は裂け、水が噴き出し、岩は割れ裂けて、谷底にころげ入る。渚を漕ぐ船は波にただよい、道ゆく馬は足もとを踏み迷う。都のほとりでは、在々所々、堂舎塔廟、一つとして無事なものはない。あるものはこわれ、あるものは倒れてしまった。塵灰が立ちのぼって、盛んな煙のごとくである。大地が割れ、家のこわれていく音は、雷の音といささかもかわらない。家の中にいれば、たちまち押しつぶされそうになる。外に走り出せば、地面が割れて裂けてゆく。羽がないので、空も飛べない。龍であったならば、空の雲にも乗れようが・・・。恐ろしいことの中で、もっと恐ろしいのは、ただただ地震なのだとはっきりわかったのでありました
こんなふうに、激しく大地が揺れることは、しばらくのことでおさまったけれど、その余震は当分絶えることがなかった。普段なら、驚くほどの地震が、二、三十回、揺れない日はない。十日、二十日過ぎていくと、ようやく間遠となり、ある日は一日に四、五回、もしくは一日おき、二、三日に一回など、その余震はおよそ三か月ほど続いたでありましょうか。
(中略)昔、斉衡のころとか、大きな地震があって、東大寺の大仏の御首が落ちたなどという、大変なこともありましたけれども、それでも今回の地震のひどさには及ばないという。当座は、人々すべてこの世のむなしさを述べて、少しは心の濁りも薄まるかとも見えたけれど、月日が重なり、年が経った後では、口に出して言う人さえいなくなってしまった』
東日本大震災で我々が目の当たりにした津波、山崩れ、液状化など、同じような光景が描写されているのがお分かりただけると思う。震災前に読んだときは正直なところ読み流した記述であったが、震災で映像や写真を見た後に読み返した時には、方丈記の記述の光景が目に浮かぶようにビビッドに頭に入ってきた
また、最後の部分は、喉元過ぎるとすぐに忘れてしまう人間の性のようなものを指摘している記述だ。今も昔も人は変わらない
同時代の物語である『平家物語』にもこの地震の記述はある。以下に原文を引用する(出典:『平家物語』作者不詳。梶原正昭・山下宏明校注。岩波文庫 第四巻)。『平家物語』の巻第十二の「大地震」という章からの抜粋である。ちなみにこの巻第十二は、源義経が兄の頼朝に追われて都落ちする部分でもある
こちらは訳文がないので原文のみの引用となるが、おおよそ理解することはできると思う。なお、( )内に岩波文庫の原文の振り仮名と脚注、および私の補注と拙訳を記した
『平家みなほろびはてて、西国もしづまりぬ。国は国司(こくし)にしたがひ、庄は領家(りょうけ)のまゝなり(平氏の滅亡により、地方の国は国司の統治となり、荘園は本来の領主の管理にもどった)。上下安堵(じょうげあんど)しておぼえし程に、同(おなじき。元暦二年、1185年のこと)七月九日の午刻(うまのこく。正午のこと)ばかりに、大地おびただしくうごいて良(やや)久し。赤県(せきけん。都のこと)のうち、白河のほとり(鴨川の東岸地域のこと)、六勝寺(ろくしょうじ)、皆やぶれくづる(すべて倒壊したという意味)。九重の塔も、うへ六重ふり落とす(九重の塔の上の六層が落ちたという意味)。得長寿院(とくじょうじゅいん。平忠盛が建立した寺)も、三十三間の御堂(みどう。得長寿院にあった三十三間堂。現存の三十三間堂は平清盛が建立した蓮華王院のお堂)を、十七間までふりたふす(振り倒した)。皇居をはじめて、人々の家々、すべて在々所々の神社・仏閣、あやしの民屋(みんおく。卑賎な人々の住む民家)、さながらやぶれくづる(すっかり倒壊した)。くづるゝ音はいかづち(雷のこと)のごとく、あがる塵(ちり)は、煙のごとし。天暗うして、日の光も見えず。老少ともに魂を消し(驚き恐れること)、朝衆(ちょうしゅう。朝廷に仕える人や一般の人々のこと)悉(ことごと)く心を尽す(不安に思うこと)。又遠国(おんごく)・近国もかくのごとし。大地さけて水わき出て、盤石(ばんじゃく)われて谷へまろぶ(転がり落ちること)。山くづれて河をうづみ(埋めること)、海たゞよひて浜をひたす(津波が押し寄せて浜を覆い浸すこと)。汀(なぎさ)こぐ船はなみにゆられ、陸(くが)ゆく駒(馬のこと)は足のたてどを失へり(どう足を踏んでよいか定めかねた)。洪水みなぎり来たらば、丘にのぼっても、などかたすからざらむ(まったく助かるすべもない)。猛火(みょうか)もえ来たらば、河をへだてても、しばしもさんぬべし(少しも避けることができない)。たゞかなしかりけるは大地震也(なり)。鳥にあらざれば、空をもかけりがたく、竜にあらざれば、雲にも又のぼりがたし。白河・六波羅・京中にうちうづまれて(家屋などの下敷きになって)、死ぬるもの、いくらといふ数を知らず(死者の数は計り知れない)。(中略)
昔、文徳(もんどく)天皇の御宇(ぎょう)、斉衡(さいこう)三年(正しくは斉衡二年で855年)三月八日の大地震には、東大寺の仏の御(おん)ぐしをふりおとしたりけるとかや(首が振り落とされたとか)。(後略)』
いかがだろうか。阪神淡路や東日本などの大地震と同じような状況が記されているのがお分かりいただけると思う。次回は、別の古典である『太平記』に記された大地震の記憶を紹介したい